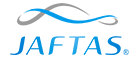進め方が分かるフローチャート:PHASE 1
EPA/FTA利用の確認
お役立ちサイト
FTA Port:世界の税関 – 関税率検索サイト
EPA/FTAに必要な情報を輸入国税関のホームページで確認できるサイト
できるコト
✔ 各国のHSコードの検索
✔ 各国の通常の関税率・EPA税率の検索
✔ 各国の事前教示制度の検索
※輸入国税関のホームページへのリンクとなるため、上記のうち何が検索可能かは、各国により異なります
こんな方におすすめ!
✔ 輸入者へ確認する上で情報整理をしたい方
✔ 輸入者から入手した情報について確認したい方
日本税関:輸出統計品目表
日本の輸出通関のために用いるHSコードを特定する際の品目表が掲載されているサイト
できるコト
✔ HSコード(6桁)の確認
✔ 日本からの輸出における統計細分(7桁目以降)の確認
こんな方におすすめ!
✔ 輸出品のHSコードの候補を調べたい方
FedEx Trade Networks/JETRO:World Tariff
最新年次版のHSコードをキーにして、MFN税率とEPA税率を確認できるサイト
できるコト
✔ 各国のMFN税率・EPA税率の確認
✔ 複数協定のEPA税率比較
✔ 各協定のEPA譲許表
こんな方におすすめ!
✔ 輸入国での税率を確認したい方
✔ EPA/FTAを利用するとメリットがあるのか知りたい方
✔ 利用協定を確定するため関税率比較をしたい方
※「WorldTariff」は米国FedEx Trade Networks社が有料で提供している世界の関税率情報データベースです。
JETROと同社との契約で、日本の居住者はどなたでも、同社のサイトから無料で「WorldTariff」をご利用いただけます。
初めてデータベースを利用する場合にはユーザー登録が必要です。ユーザー登録はこちらから。
※必ずしも最新の情報でアップデートされていない可能性もありますので、輸入国税関の情報の確認用としてご活用ください。
International Trade Centre:Rules of Origin Facilitator
最新年次版のHSコードをキーにして、MFN税率/EPA税率/PSR等を確認できるサイト
できるコト
✔ 各国のMFN税率・EPA税率の確認
✔ 複数の国からの輸入をする際のEPA税率比較
✔ 他国間協定の品目別原産地規則
こんな方におすすめ!
✔ 輸入国での税率を確認したい方
✔ EPA/FTAを利用するとメリットがあるのか知りたい方
✔ 多国間協定も含めて、利用協定を確定するために関税率比較をしたい方
※必ずしも最新の情報でアップデートされていない可能性もありますので、輸入国税関の情報の確認用としてご活用ください。
FTA Port:HS LAB
EPA/FTA原産地証明に特化したHSコードの情報提供サイト
できるコト
✔ 特定したHSコード(協定年次版HSコード)からのMFN/EPA税率
こんな方におすすめ!
✔ MFN/EPA税率を日本語のWebサイトで確認したい方