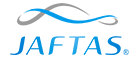進め方が分かるフローチャート:PHASE 2 原産品であることの確認_D 原産資格調査
お役立ちサイト
FTA Port:HS LAB
EPA/FTA原産地証明に特化したHSコードの情報提供サイト
できるコト
✔ 各協定年次版HSコードの検索
✔ 特定したHSコード関連の注や解説の確認
こんな方におすすめ!
✔ 各協定から輸出品の協定年次版HSコードを確認したい方
✔ 各協定からCTCを使うにあたって、構成品・材料の協定年次版HSコードの候補を知りたい方
日本税関:輸出統計品目表
日本の輸出通関のために用いるHSコードを特定する際の品目表が掲載されているサイト
できるコト
✔ 各協定年次版HSコードの検索
✔ 特定したHSコード関連の注や解説の確認
こんな方におすすめ!
✔ 調べたいHS年次を把握した上で、HSコードを確認したい方
WCO 世界関税機構:HS Tracker
HSコードの改定履歴を追跡できるサイト
できるコト
✔ HSコードのコンバージョン
✔ HSコード改定の際の変遷の確認
こんな方におすすめ!
✔ 最新のHSコードは分かっているけれど、協定年次版のHSコードを知りたい方
日本税関:原産地規則ポータル(品目別原産地規則の検索)
輸入国/協定年次版HSコードの情報から、品目別原産地規則を確認できるサイト
できるコト
✔ 利用協定の品目別原産地規則を確認できる
✔ 仕向国毎に利用できる協定の品目別原産地規則を比較することができる
こんな方におすすめ!
✔ 品目別原産地規則を確認したい方
✔ 品目別原産地規則の難易度を比較し、利用協定を決めたい方
日本商工会議所:第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル -発給システム操作編-
日本商工会議所への原産品判定依頼の手続きについて確認できる資料
できるコト
✔ 発給システムの入力方法の確認
✔ 発給システム入力時の留意点の確認
こんな方におすすめ!
✔ 初めて発給システムに入力をされる方
✔ 発給システムに入力したけど、入力した内容に不安がある方